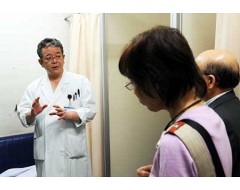- ホーム
- 特集・話題
- ケースナンバー187
- 7 遠い世界 手術考えないと主張
7 遠い世界 手術考えないと主張
秋の日はつるべ落とし。二〇〇七年十月三十一日。岡山労災病院(岡山市南区築港緑町)の南病棟三階。六人部屋の一隅にじっと横たわり、三リットルの腹水を抜き終えるころ、真っ赤な夕日が児島半島の常山に沈んでいった。
夕食後、腹水を十分の一くらいに濃縮した輸液バッグが届き、静脈点滴する再静注は夜半までかかった。軽い発熱はあったが、ショックに見舞われることはなかった。
しかし、おなかがへこんでやっと 肋骨 ( ろっこつ ) に触れるようになった、と 安堵 ( あんど ) したのもつかの間。翌日になるとまたぞろ、右わき腹がギュルギュルと騒ぎ始めた。
腹の虫が空腹を訴えているとしか聞こえないかもしれないが、自分で肝臓の位置が分かるようになっていた。明らかに肝臓が泣いている。何とも悲しげなうめき声だ。
再静注も 所詮 ( しょせん ) は対症療法。濃縮した腹水には血管に水分を引き込むアルブミンが豊富に含まれ、本来の血液循環系に戻してやることで腹水量の減少を期待できる。しかし、漏出する腹水を止められない限り、一時的な効果にとどまる。
この先いったいどうすればいいのか―。一週間後の十一月七日。谷岡洋亮医師がしたためてくれた紹介状とCT(コンピューター断層撮影)画像のフィルムを抱え、岡山大病院(同市北区鹿田町)の外科外来を訪ねた。
<肝移植の適応患者と考えられる。ついてはご高診を請う>というわけである。
話がずいぶん長くなってきた。移植手術を受ける約百三十日前である。私は初めて、執刀医となる八木孝仁医師( 肝胆膵 ( かんたんすい ) 外科講師)の診察を受けた。
この時点では、移植はまだ「遠い世界の話」だと思っていた。いや、無理にも思い込もうとしていた。
取材を通じ、ある程度の知識があり、レシピエントの方から体験をうかがう機会もあった。移植医療というものが決して「バラ色」でないことは、自分なりに分かっているつもりだった。
「移植はしないに越したことはないですよね」。今にして思えば、ずいぶん生意気を言ったものだ。岡山大の生体肝移植の症例数や成績(生存率)について尋ねた後、私は当面、手術は考えないと主張した。八木医師は否定はしなかった。
「生体(肝移植)だけは本当に異質な医療だ」。二百十例以上を手がけてなお、八木医師はそう語る。メスで差配できる領域を超えたさまざまな「社会的」困難に直面する家族の姿を見てきたに違いない。できうることなら別の道を選択した方がいい、という偽らざる気持ちがあるのだと思う。
百人患者がいれば、百通りの問題に立ち向かわなければならない。私もそれからが真の 懊悩 ( おうのう ) の日々だった。
メモ
造影CT 肝臓病患者の大半は造影剤を静脈注射してダイナミックCTという画像を撮影される。数十秒のうちに注入された造影剤は、最初は肝動脈を経由して、少し遅れて門脈を経由して、肝臓へ流入する。血流路の違いにより、強く染まる肝組織が異なり、特に腫瘍(しゅよう)、がんを鑑別するのに有効。まれにヨード造影剤の副作用によるショックに陥る人があり、撮影前に必ずアレルギーの既往を問診される。
※登場する人物・団体は掲載時の情報です。
夕食後、腹水を十分の一くらいに濃縮した輸液バッグが届き、静脈点滴する再静注は夜半までかかった。軽い発熱はあったが、ショックに見舞われることはなかった。
しかし、おなかがへこんでやっと 肋骨 ( ろっこつ ) に触れるようになった、と 安堵 ( あんど ) したのもつかの間。翌日になるとまたぞろ、右わき腹がギュルギュルと騒ぎ始めた。
腹の虫が空腹を訴えているとしか聞こえないかもしれないが、自分で肝臓の位置が分かるようになっていた。明らかに肝臓が泣いている。何とも悲しげなうめき声だ。
再静注も 所詮 ( しょせん ) は対症療法。濃縮した腹水には血管に水分を引き込むアルブミンが豊富に含まれ、本来の血液循環系に戻してやることで腹水量の減少を期待できる。しかし、漏出する腹水を止められない限り、一時的な効果にとどまる。
この先いったいどうすればいいのか―。一週間後の十一月七日。谷岡洋亮医師がしたためてくれた紹介状とCT(コンピューター断層撮影)画像のフィルムを抱え、岡山大病院(同市北区鹿田町)の外科外来を訪ねた。
<肝移植の適応患者と考えられる。ついてはご高診を請う>というわけである。
話がずいぶん長くなってきた。移植手術を受ける約百三十日前である。私は初めて、執刀医となる八木孝仁医師( 肝胆膵 ( かんたんすい ) 外科講師)の診察を受けた。
この時点では、移植はまだ「遠い世界の話」だと思っていた。いや、無理にも思い込もうとしていた。
取材を通じ、ある程度の知識があり、レシピエントの方から体験をうかがう機会もあった。移植医療というものが決して「バラ色」でないことは、自分なりに分かっているつもりだった。
「移植はしないに越したことはないですよね」。今にして思えば、ずいぶん生意気を言ったものだ。岡山大の生体肝移植の症例数や成績(生存率)について尋ねた後、私は当面、手術は考えないと主張した。八木医師は否定はしなかった。
「生体(肝移植)だけは本当に異質な医療だ」。二百十例以上を手がけてなお、八木医師はそう語る。メスで差配できる領域を超えたさまざまな「社会的」困難に直面する家族の姿を見てきたに違いない。できうることなら別の道を選択した方がいい、という偽らざる気持ちがあるのだと思う。
百人患者がいれば、百通りの問題に立ち向かわなければならない。私もそれからが真の 懊悩 ( おうのう ) の日々だった。
メモ
造影CT 肝臓病患者の大半は造影剤を静脈注射してダイナミックCTという画像を撮影される。数十秒のうちに注入された造影剤は、最初は肝動脈を経由して、少し遅れて門脈を経由して、肝臓へ流入する。血流路の違いにより、強く染まる肝組織が異なり、特に腫瘍(しゅよう)、がんを鑑別するのに有効。まれにヨード造影剤の副作用によるショックに陥る人があり、撮影前に必ずアレルギーの既往を問診される。
(2009年05月25日 更新)