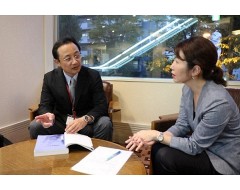- ホーム
- 特集・話題
- 命を継ぐ 臓器移植法20年 岡山の現場から
- (9)当たり前の医療 経験者の発信が近道に
(9)当たり前の医療 経験者の発信が近道に
インターネット上の腎移植患者向け医療情報サイト「メディプレス腎移植」。インタビューのページには、あどけない表情の赤ちゃんと一緒に、幸せそうに写真に納まる女性の姿があった。
30代。自己免疫疾患を発病したのは10歳の時だった。腎機能が徐々に低下し、入退院を繰り返した。命が危険にさらされ、ICU(集中治療室)に入ったこともあるという。
人生が大きく変わったのが移植だった。「子どもも授かり、充実した毎日を送っています」。サイト上で感謝の気持ちを語っている。
別のページで思いを伝えているのは、夫が妻へのドナー(臓器提供者)となった夫婦=ともに60代=だ。
妻は、夫の体を傷つけることへの申し訳なさ、苦しかった食事療法を振り返りながらも「移植後は旅行にも行けるようになった」と喜びを語り、移植を待つ患者に「前向きに希望を持って頑張って」とエールを送っている。
感謝の気持ち
ともに岡山大病院(岡山市北区鹿田町)で生体腎移植を受けた。経験者ならではのリアルな声からは、湧き立つような生への喜びが伝わってくる。
移植臓器の中でも腎臓は、待機患者を取り巻く環境が過酷だ。10月末現在、全臓器で1万4千人余りいる患者のうち、腎臓を待つのは約1万2千人で9割近くに上る。一方、年間の腎移植数は、脳死や心停止後のドナーからと生体間を合わせて1600例程度。移植を待つ期間は平均15年ほどで、20年以上という患者も800人近くいる。
「移植への理解が深まれば、脳死ドナーも増えると思う」と話すのは、岡山大病院で腎移植を担当する荒木元朗講師(46)=泌尿器科。2002年から5年間、米国へ留学し、腎移植を学んだ。
移植先進地で見たのは、圧倒的な症例数だった。提供システムや院内体制も充実していた。驚いたのは、移植患者自身が、元気な様子をさまざまなメディアで伝える姿だった。「日本ではまず見られない光景だった。ドナーが多い理由も、そこなんだと思った」
移植後の元気な姿とドナーへの感謝の気持ちを知ることで、ドナー家族も幸せを得られる。「特別ではない、当たり前の医療にしていくには、米国のように経験者に語ってもらうのが近道。国民の意識を変える力は、患者自身が持っている」と話す。
体験を元に、「メディプレス腎移植」に登場した30代女性、60代夫婦らに対し、主治医として“出演”を依頼した。
一人でも多く
50年近く前に行われた日本初の心臓移植は、ドナーの脳死判定の妥当性に疑念が生じ、世論の批判を浴びた。わが国の移植医療はそんなマイナスからのスタートだった。
その反省を踏まえ誕生したのが臓器移植法だ。「脳死は人の死」という新たな死の概念を法で定めた内容は、国内で大論争を巻き起こしたが、移植医療という重い扉を開いた。
9月、北海道旭川市で開かれた日本移植学会総会。臓器移植法の施行20年をテーマにしたシンポジウムで、登壇した医師が希望を込め、日本の移植医療の未来予想を語った。
「受け持ちの患者が助からないと判断した医師は『そういえば臓器提供の意思はあっただろうか。家族に尋ねてみよう』。対する家族は『残念です。では提供の申し出はどうしたらいいでしょうか』。そんなふうに自然に、そして抵抗なく考えられる社会になることではないだろうか」
臓器提供を希望する、しない。移植を希望する、しない。移植医療には、そうした権利が存在する。
一人でも多くの人が、命に思いをはせ、家族の姿を頭に描きながら、自分なりの結論を導き出していく。それが特別な医療から、当たり前の医療へと変わるための第一歩でもある。=おわり
※登場する人物・団体は掲載時の情報です。
30代。自己免疫疾患を発病したのは10歳の時だった。腎機能が徐々に低下し、入退院を繰り返した。命が危険にさらされ、ICU(集中治療室)に入ったこともあるという。
人生が大きく変わったのが移植だった。「子どもも授かり、充実した毎日を送っています」。サイト上で感謝の気持ちを語っている。
別のページで思いを伝えているのは、夫が妻へのドナー(臓器提供者)となった夫婦=ともに60代=だ。
妻は、夫の体を傷つけることへの申し訳なさ、苦しかった食事療法を振り返りながらも「移植後は旅行にも行けるようになった」と喜びを語り、移植を待つ患者に「前向きに希望を持って頑張って」とエールを送っている。
感謝の気持ち
ともに岡山大病院(岡山市北区鹿田町)で生体腎移植を受けた。経験者ならではのリアルな声からは、湧き立つような生への喜びが伝わってくる。
移植臓器の中でも腎臓は、待機患者を取り巻く環境が過酷だ。10月末現在、全臓器で1万4千人余りいる患者のうち、腎臓を待つのは約1万2千人で9割近くに上る。一方、年間の腎移植数は、脳死や心停止後のドナーからと生体間を合わせて1600例程度。移植を待つ期間は平均15年ほどで、20年以上という患者も800人近くいる。
「移植への理解が深まれば、脳死ドナーも増えると思う」と話すのは、岡山大病院で腎移植を担当する荒木元朗講師(46)=泌尿器科。2002年から5年間、米国へ留学し、腎移植を学んだ。
移植先進地で見たのは、圧倒的な症例数だった。提供システムや院内体制も充実していた。驚いたのは、移植患者自身が、元気な様子をさまざまなメディアで伝える姿だった。「日本ではまず見られない光景だった。ドナーが多い理由も、そこなんだと思った」
移植後の元気な姿とドナーへの感謝の気持ちを知ることで、ドナー家族も幸せを得られる。「特別ではない、当たり前の医療にしていくには、米国のように経験者に語ってもらうのが近道。国民の意識を変える力は、患者自身が持っている」と話す。
体験を元に、「メディプレス腎移植」に登場した30代女性、60代夫婦らに対し、主治医として“出演”を依頼した。
一人でも多く
50年近く前に行われた日本初の心臓移植は、ドナーの脳死判定の妥当性に疑念が生じ、世論の批判を浴びた。わが国の移植医療はそんなマイナスからのスタートだった。
その反省を踏まえ誕生したのが臓器移植法だ。「脳死は人の死」という新たな死の概念を法で定めた内容は、国内で大論争を巻き起こしたが、移植医療という重い扉を開いた。
9月、北海道旭川市で開かれた日本移植学会総会。臓器移植法の施行20年をテーマにしたシンポジウムで、登壇した医師が希望を込め、日本の移植医療の未来予想を語った。
「受け持ちの患者が助からないと判断した医師は『そういえば臓器提供の意思はあっただろうか。家族に尋ねてみよう』。対する家族は『残念です。では提供の申し出はどうしたらいいでしょうか』。そんなふうに自然に、そして抵抗なく考えられる社会になることではないだろうか」
臓器提供を希望する、しない。移植を希望する、しない。移植医療には、そうした権利が存在する。
一人でも多くの人が、命に思いをはせ、家族の姿を頭に描きながら、自分なりの結論を導き出していく。それが特別な医療から、当たり前の医療へと変わるための第一歩でもある。=おわり
(2017年11月27日 更新)
タグ:
腎臓・尿路・性器