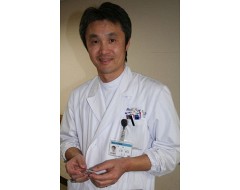- ホーム
- 特集・話題
- ケースナンバー187
- 49 ステント 肝静脈支える金剛杖
49 ステント 肝静脈支える金剛杖
2009年が明けた。岡山市内の実家で両親、ドナーの弟とともに家族4人で新年を迎えた。移植を受けていなかったら、新しい年を見ることはできなかっただろう。感謝。ただ、ひたすら、感謝。
だけれど、悟りを開くどころか、懊悩(おうのう)は深まるばかり。「只管(しかん)打(た)坐(ざ)」と修行に励もうとしても、背中から足の先までしびれていては、とてもかなわない。
胸椎(きょうつい)硬膜外膿瘍(のうよう)により、背中を切開して膿(うみ)を郭清(かくせい)した緊急手術(2006年8月)の後、ずっとしびれたまま。移植後も軽くなるどころか増悪している。
24時間絶え間ない痛みやしびれは本当につらい。医学用語で「不定愁訴」扱いされることもしばしばだが、不定どころか、常に一定の痛みやしびれを訴えているのだが…。
私の場合、MRI(磁気共鳴画像装置)検査でも異常は見られないが、体感的には、入院して寝込むたびにしびれが強くなった。細胞、分子のレベルで見れば、何かが起きているに違いない。
その上、IVR(放射線診断技術の治療的応用)の血管内手術を繰り返してきたのに、相変わらず腹水がたまり続ける。術後半年をめどに仕事に復帰するつもりだったが、延び延びになり、職場にも迷惑をかけていた。
肝機能値はおおむね良好で、体を動かすことによって悪化するとは考えられないが、一日の大半を横になって過ごした。肝硬変時に染みついた腹水への恐怖としびれが重いくびきとなり、立ち上がれないでいた。
09年1月21日、岡山大病院のIVR外来で三村秀文医師(放射線科講師)の診察を受けた。バルーン(風船)カテーテルで何度広げても、ねじれた肝静脈はすぐにすぼまってしまう。6度目のIVRでどう治療するか―。
移植巡礼の最難所にさしかかっている。三村医師らIVRチームが用意してくれた「金剛杖(こんごうづえ)」は、筒状の網目になった長さ約4センチ、直径約1センチの金属製ステントだった。
ステントは心臓の冠状動脈をはじめ、さまざまな血管や気管、消化管の狭窄(きょうさく)の治療に用いられる。
肝移植後は胆道系のトラブルが多い。私も胆管狭窄が見つかり、プラスチックのチューブステントを挿入した(連載47回参照)。一度入れ替えた後、狭窄はほぼ解消し、抜去してもらっていた。
今度は肝静脈を対象にステントを入れようというのだが、非常に珍しく、岡山大病院では初症例らしい。
ステントの素材は形状記憶合金のナイチノール(ニッケル・チタン合金)。プラスチックと違って自己拡張力があり、うまく狭窄部に留置できれば、内側から血管を広げ、支え続けてくれるはずだ。
しかし、ひとたび留置すると入れ替えはできない。ステントが外れて血管内を移動したり、内面に新しい膜ができる内膜肥厚や血栓が生じて再び狭窄する恐れもある。
三村医師は危険性を説明した上で、「その場合にもいろいろ打つ手はあります」と励ましてくれた。
メモ
金剛杖 四国遍路には、菅笠(すげがさ)や白衣(びゃくえ)とともに金剛杖が欠かせない。四角の白木の頭部(五輪形)に梵字(ぼんじ)が書かれ、弘法大師が宿るとされている。直接手で触れないよう、普段は白布や金襴(きんらん)で巻いておく。十夜ケ橋(とよがはし=愛媛県大洲市)の下で一夜を明かしたと伝えられる大師を敬い、遍路は橋の上で杖をつかないのが習わしとなっている。
※登場する人物・団体は掲載時の情報です。
だけれど、悟りを開くどころか、懊悩(おうのう)は深まるばかり。「只管(しかん)打(た)坐(ざ)」と修行に励もうとしても、背中から足の先までしびれていては、とてもかなわない。
胸椎(きょうつい)硬膜外膿瘍(のうよう)により、背中を切開して膿(うみ)を郭清(かくせい)した緊急手術(2006年8月)の後、ずっとしびれたまま。移植後も軽くなるどころか増悪している。
24時間絶え間ない痛みやしびれは本当につらい。医学用語で「不定愁訴」扱いされることもしばしばだが、不定どころか、常に一定の痛みやしびれを訴えているのだが…。
私の場合、MRI(磁気共鳴画像装置)検査でも異常は見られないが、体感的には、入院して寝込むたびにしびれが強くなった。細胞、分子のレベルで見れば、何かが起きているに違いない。
その上、IVR(放射線診断技術の治療的応用)の血管内手術を繰り返してきたのに、相変わらず腹水がたまり続ける。術後半年をめどに仕事に復帰するつもりだったが、延び延びになり、職場にも迷惑をかけていた。
肝機能値はおおむね良好で、体を動かすことによって悪化するとは考えられないが、一日の大半を横になって過ごした。肝硬変時に染みついた腹水への恐怖としびれが重いくびきとなり、立ち上がれないでいた。
09年1月21日、岡山大病院のIVR外来で三村秀文医師(放射線科講師)の診察を受けた。バルーン(風船)カテーテルで何度広げても、ねじれた肝静脈はすぐにすぼまってしまう。6度目のIVRでどう治療するか―。
移植巡礼の最難所にさしかかっている。三村医師らIVRチームが用意してくれた「金剛杖(こんごうづえ)」は、筒状の網目になった長さ約4センチ、直径約1センチの金属製ステントだった。
ステントは心臓の冠状動脈をはじめ、さまざまな血管や気管、消化管の狭窄(きょうさく)の治療に用いられる。
肝移植後は胆道系のトラブルが多い。私も胆管狭窄が見つかり、プラスチックのチューブステントを挿入した(連載47回参照)。一度入れ替えた後、狭窄はほぼ解消し、抜去してもらっていた。
今度は肝静脈を対象にステントを入れようというのだが、非常に珍しく、岡山大病院では初症例らしい。
ステントの素材は形状記憶合金のナイチノール(ニッケル・チタン合金)。プラスチックと違って自己拡張力があり、うまく狭窄部に留置できれば、内側から血管を広げ、支え続けてくれるはずだ。
しかし、ひとたび留置すると入れ替えはできない。ステントが外れて血管内を移動したり、内面に新しい膜ができる内膜肥厚や血栓が生じて再び狭窄する恐れもある。
三村医師は危険性を説明した上で、「その場合にもいろいろ打つ手はあります」と励ましてくれた。
メモ
金剛杖 四国遍路には、菅笠(すげがさ)や白衣(びゃくえ)とともに金剛杖が欠かせない。四角の白木の頭部(五輪形)に梵字(ぼんじ)が書かれ、弘法大師が宿るとされている。直接手で触れないよう、普段は白布や金襴(きんらん)で巻いておく。十夜ケ橋(とよがはし=愛媛県大洲市)の下で一夜を明かしたと伝えられる大師を敬い、遍路は橋の上で杖をつかないのが習わしとなっている。
(2010年05月31日 更新)