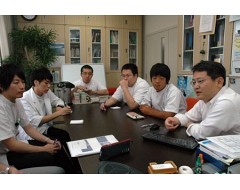第7部 あすへつなぐ (8) 心のケア あと半歩 患者に近づく
患者は「不安」を抱え生きている。がんの場合はなおさらだ。告知、余命宣告、再発の恐れ…。人生を大きく狂わせる事態が、いつ来るとも分からない。
「頑張れ、なんてとても言えない」。金田病院(真庭市西原)の三村卓司副院長(50)は言う。
「患者はずっとフルマラソンを走っているのと同じ。僕ら医師に必要なのは、患者の気持ちを理解し、優しさを持って接すること」
半年前に出会った女性は40代で末期がんだった。病室で医師や看護師にも本音を見せず、壁をつくっているように感じた。
「つらいよね」
女性が変わったのは、三村副院長がそう問い掛けた時だ。小学生の幼い子どもを後に残す不安。友人に弱った姿を見せたくないとの思い。抑えていた気持ちが一気に言葉になってあふれ出た。
まだ子どもに、病気のことをきちんと伝えられずにいた。この日を境に、女性は自分を冷静に見詰め始め、数カ月後に亡くなった。
~
「つらいことを(こちらも)分かっていると伝えるだけで、患者は救われた気持ちになり、苦しみは癒える」。岡山大大学院の内富庸介教授(51)は指摘する。
「サイコオンコロジー(精神 腫瘍 ( しゅよう ) 学)」が専門。がん患者や家族のQOL(生活の質)向上を研究する、国内でまだ新しい分野だ。
患者の気持ちに配慮しながら、余命や治療の中断といった「悪い知らせ」をどう伝えるか。内富教授はそのノウハウをまとめ、2005年に「SHARE(シェア)」というトレーニングプログラムを開発した。
患者の目を見て、礼儀正しく話す▽患者を支える言葉を添える▽今後の治療や生活に関する情報を知らせる▽最後まで見捨てないことを伝える―などがポイント。
このプログラムに基づき、日本サイコオンコロジー学会などはコミュニケーション技術研修会を開催、これまでに全国で約200人の医師が受講した。
その一人の三村副院長は「残された時間をどう過ごしたいのか、家族は何を思っているのか。研修会では、医師は相手の気持ちをくみとったり、引き出す努力が求められていると強く感じた」と話す。
~
SHAREのルーツは、内富教授が今年3月まで勤めた国立がんセンター東病院(千葉県柏市)にある。
同病院は1992年の開院当初から、すべての患者にがんを告知している。当時、米国では主流だったが、国内はまだ賛否が割れていた。
だが数年後、告知した患者の2割がうつになり、残りも心に大きなダメージを受けたことが分かった。医師が告知後に十分な心のケアを怠ったり、告知が事務的になっていたことが原因だった。
内富教授らは99年、患者ら約600人にアンケート。患者としてどう伝えてほしいかを探り、SHAREにまとめていった。
「温かい一言を添えるだけで、患者の受け止め方は大きく変わる。そうした心のケアが抜け落ちていた」と内富教授。「でも、それは医師が最も苦手とする部分なんです」
~
今月21日。岡山大鹿田キャンパス(岡山市北区鹿田町)。医学部5年生を前に、内富教授の講義が始まった。
「インフォームドコンセントは十分な説明と同意という意味がある。でもその間に、患者と医師の『情』、気持ちをぜひ加えてほしい」
次代を担う医学生に思いを託したい―。将来はカリキュラムにSHAREを取り入れる計画だ。
「もう半歩。あと少しでいいから、医師は患者に歩み寄ってほしい。そうすれば、思いの『ずれ』は必ず埋められる」
シリーズ終わり
※登場する人物・団体は掲載時の情報です。
「頑張れ、なんてとても言えない」。金田病院(真庭市西原)の三村卓司副院長(50)は言う。
「患者はずっとフルマラソンを走っているのと同じ。僕ら医師に必要なのは、患者の気持ちを理解し、優しさを持って接すること」
半年前に出会った女性は40代で末期がんだった。病室で医師や看護師にも本音を見せず、壁をつくっているように感じた。
「つらいよね」
女性が変わったのは、三村副院長がそう問い掛けた時だ。小学生の幼い子どもを後に残す不安。友人に弱った姿を見せたくないとの思い。抑えていた気持ちが一気に言葉になってあふれ出た。
まだ子どもに、病気のことをきちんと伝えられずにいた。この日を境に、女性は自分を冷静に見詰め始め、数カ月後に亡くなった。
~
「つらいことを(こちらも)分かっていると伝えるだけで、患者は救われた気持ちになり、苦しみは癒える」。岡山大大学院の内富庸介教授(51)は指摘する。
「サイコオンコロジー(精神 腫瘍 ( しゅよう ) 学)」が専門。がん患者や家族のQOL(生活の質)向上を研究する、国内でまだ新しい分野だ。
患者の気持ちに配慮しながら、余命や治療の中断といった「悪い知らせ」をどう伝えるか。内富教授はそのノウハウをまとめ、2005年に「SHARE(シェア)」というトレーニングプログラムを開発した。
患者の目を見て、礼儀正しく話す▽患者を支える言葉を添える▽今後の治療や生活に関する情報を知らせる▽最後まで見捨てないことを伝える―などがポイント。
このプログラムに基づき、日本サイコオンコロジー学会などはコミュニケーション技術研修会を開催、これまでに全国で約200人の医師が受講した。
その一人の三村副院長は「残された時間をどう過ごしたいのか、家族は何を思っているのか。研修会では、医師は相手の気持ちをくみとったり、引き出す努力が求められていると強く感じた」と話す。
~
SHAREのルーツは、内富教授が今年3月まで勤めた国立がんセンター東病院(千葉県柏市)にある。
同病院は1992年の開院当初から、すべての患者にがんを告知している。当時、米国では主流だったが、国内はまだ賛否が割れていた。
だが数年後、告知した患者の2割がうつになり、残りも心に大きなダメージを受けたことが分かった。医師が告知後に十分な心のケアを怠ったり、告知が事務的になっていたことが原因だった。
内富教授らは99年、患者ら約600人にアンケート。患者としてどう伝えてほしいかを探り、SHAREにまとめていった。
「温かい一言を添えるだけで、患者の受け止め方は大きく変わる。そうした心のケアが抜け落ちていた」と内富教授。「でも、それは医師が最も苦手とする部分なんです」
~
今月21日。岡山大鹿田キャンパス(岡山市北区鹿田町)。医学部5年生を前に、内富教授の講義が始まった。
「インフォームドコンセントは十分な説明と同意という意味がある。でもその間に、患者と医師の『情』、気持ちをぜひ加えてほしい」
次代を担う医学生に思いを託したい―。将来はカリキュラムにSHAREを取り入れる計画だ。
「もう半歩。あと少しでいいから、医師は患者に歩み寄ってほしい。そうすれば、思いの『ずれ』は必ず埋められる」
シリーズ終わり
(2010年06月27日 更新)