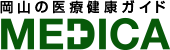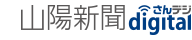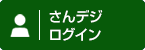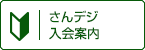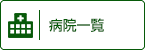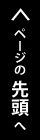声のトラブルは治療できる 一人で悩まず耳鼻咽喉科受診を

耳鼻咽喉・頭頸部外科部長
原 浩貴
1989年、山口大学医学部卒。医学博士。米チュレーン大病理学教室留学。帰国後、山口大学耳鼻咽喉科講師、准教授を経て2017年4月から川崎医科大学耳鼻咽喉科学主任教授。2021年4月より川崎医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学主任教授。専門は音声外科、睡眠時無呼吸症、喉頭癌(がん)、嚥下障害。
⇒インタビュー動画
-音声障害とはどのような症状が出るのか。
音声障害は「音質,声の高さ,声の大きさ,発声努力などの変化により、コミュニケーションを損なう、あるいは声のQOL(生活の質)が低下すること」と定義されている。簡単に言えば、声がかれてしまい、いつもの自分の声ではないという自覚症状が出た場合がすべて音声障害。声がかれる、出したい声が出ない、声が震えてしまう、大きな声が出ない、歌うときに一定の音だけ出ないといった症状がある。
-原因は?
医学的には九つの分類に分けられるが、大きく四つの原因がある。①風邪や、大声を出した時、声帯に炎症が起きて声が出なくなる場合で、しばしば経験する。②のどに負担をかける発声法や生活習慣が原因で、声帯の表面に異常ができる場合で、手術を必要とすることも多い。たんこぶのような血腫(声帯ポリープ)「ペンだこ」のような結節などが有名であるが、喫煙は声帯の表面が水膨れのようになるポリープ様声帯や、声帯のがんを引き起こす危険があるので注意してもらいたい。③甲状腺や肺、食道の病変や手術の後に神経麻痺を起こして声帯の動き自体が悪くなる場合(反回神経麻痺)、あるいは加齢のために声帯が萎縮している場合、左右の声帯が閉鎖しないために声を出そうとしても息漏れが強く大きな声がだせなくなる。この場合は、局所麻酔で音声を聞きながら行う音声外科手術の適応になる。④声を出すために重要な声帯の筋肉に、自分の意志とは無関係に力が入ってしまうため、つまり声や、声のとぎれが強くなり、仕事や日常生活において会話が円滑に行えず、社会生活で大きな支障をきたす原因不明の病気で、痙攣(けいれん)性発声障害がある。根本治療のない難治性疾患であるが、本邦では保険適応になっている2つの治療法がある。⑤強い心理的ストレスが掛かったときにも声が出なくなる。このように音声障害の中には悪性が原因のものもあるため、声が出なくなったときには注意が必要だ。また、治療で改善する場合も多いため、専門医師の受診を勧める。
―痙攣性発声障害の二つの治療とは?
痙攣性発声障害は、声を出すために重要な声帯の筋肉に、自分の意志とは無関係に力が入ってしまうことにより仕事や日常生活において会話が円滑に行えず、社会生活で大きな支障をきたす原因不明で根本治療のない難治性疾患である。本邦では、認可された施設において、声帯へのA型ボツリヌス毒素の局所注入治療と、いわゆるのど仏の骨である甲状軟骨にチタンブリッジを埋め込む喉頭形成術の2つの方法が行われている。当科はいずれの治療も実施可能施設であり、県外からの受診者もある。どちらの方法も治療効果は良好なため、悩んでおられる患者さんは、ぜひ受診して相談して頂きたい。
-どのように診断するのか。
詳細な問診を行った上で、声を聞き、ファイバースコープで病変の有無を確認したり、ストロボ光で声帯の細かな動きを診断したり、必要な場合は声の音響解析をしたりする。どこで問題が起きているのかを他覚的に診て、治療方針を決める。
-病院を受診するタイミングは?
風邪などで2日間以上声が出ない、声のトラブルが2週間以上続く場合は耳鼻科を受診してほしい。
-どのような治療方法があるのか。
炎症がある場合は吸入療法や、声を一定期間出さない沈黙療法が有効だ。しかし、長すぎる沈黙療法は帰って有害で有り、専門家の意見を聞いて、治療日数を決めてほしい。
ポリープができたり、声帯ひだにトラブルがある場合は、全身麻酔で口の中から顕微鏡や内視鏡で声帯を拡大視して手術をしたり、外来で電子内視鏡を鼻から入れて局所麻酔で手術をすることもある。さらに、声帯麻痺の治療の場合は局所麻酔で患者さんと話をしながら、声帯の周辺にインプラントを入れて声の改善を図ることが多い。音声障害の原因と声の状況に応じて、言語聴覚士らと連携して治療に当たることもあり、患者にとって最善な治療方法を選ぶようにしている。
-生活する上で注意点は?
適度な水分補給が必要だ。仕事で声を使う人は、ペットボトル(500ミリリットル)3本分が必要だと言われている。声のトラブルを起こす人はおしゃべりな人が多い。長時間話しがちな人も気を付けてもらいたい。タバコは確実にのどを悪くするので、やめた方が良い。
―高齢者の音声障害にはどんな治療法があるか?
高齢になると、特に男性では声帯筋がやせてくるために、声がかすれたり、弱々しくなることがある。若いうちから「のどトレーニング」を行っておくことが有効であるが、高齢になってからも漢方薬などで筋力の補強をする方法もある。コラーゲンなどを注入する方法で声を改善させることもできる場合がある。
高齢者では嚥下(えんげ)障害の予防が重要な課題の一つであるが、音声障害に対するリハビリテーションは、嚥下障害の予防やリハビリテーションにもなるため、積極的に耳鼻咽喉科で相談してもらいたい。
(2021年07月30日 更新)